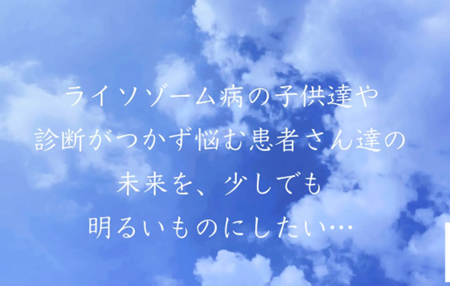神経疾患、心不全、がん診断に革新をもたらすPET診断薬を開発、「セラノスティクス」を通じた個別化医療の実現に期待
岡山大学は8月20日、ドイツ・ヴュルツブルク大学との国際共同研究を通じて、神経疾患、心不全、がんなどの早期診断や治療評価を革新する次世代型の高精細PET診断薬の開発に成功したと発表しました。
この研究は、岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)の能勢直子助教と樋口隆弘教授(特任)らが所属する研究グループが、「大学改革促進のための国際研究拠点形成プログラム(RECTOR)」の分子イメージングプロジェクトの一環として推進したものです。
開発されたPET診断薬は主に二種類あります。ひとつは、交感神経の分子マーカー「ノルエピネフリン輸送体(NET)」を標的とした新規PET診断薬です。これはパーキンソン病(指定難病6)や心不全の早期・精密診断に加え、交感神経系腫瘍の診断と治療評価に革新をもたらすことが期待されています。この診断薬は、日本で世界初の臨床研究が進行中で、ドイツでも初期段階の臨床応用が始まっています。将来的には、診断情報に基づいて最適な治療を同時に行う「セラノスティクス」につながると考えられています。
もうひとつは、放射性診断薬「F-18標識化合物[18F]DR29」です。この診断薬は、血圧や体内の水分バランスを調整するアンジオテンシンIIタイプ1受容体(AT1R)に高選択的に結合します。これにより、これまで画像化が困難だった心筋・腎臓の微細な病変や、がんの悪性度に関わる分子変化を高精細に可視化することが可能になりました。前臨床研究において安全性と有効性が実証されており、今後の臨床試験による実用化への期待が非常に高まっています。
これらの画像診断技術は、神経疾患、心不全、がんの分子レベルでの病態把握を可能にし、個別化医療やセラノスティクス医療の実現に貢献すると期待されます。岡山大学は今後もRECTORプログラムを核として国際連携を深め、次世代医療を支える革新技術の社会実装に貢献していく方針です。
岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)の樋口隆弘教授はプレスリリースにて、「日本とドイツそれぞれの強みを生かし、基礎から臨床応用まで一気通貫で推進してこられたこと自体が画期的であり、大きな成果だと考えています。神経疾患や心不全、がんといった幅広い疾患領域において、これらの PET 診断薬が早期診断や治療評価、さらにはセラノスティクスを通じた個別化医療の実現に貢献することを強く期待しています」と述べています。
なお、同研究の成果は、米国心臓協会(AHA)発行の医学雑誌「Hypertension」に8月8日付で掲載されました。