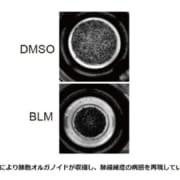難病患者を対象とした災害対策セミナー開催
昨年は、日本各地で大きな地震や台風による被害が出ました。そうした被害に普段から備えるために、「 難病をもつ人の災害の備え~地震や水害などに備えるため、今できることから始めよう~」をテーマにした講演会が、2020年2月1日に東京都(江東区)にて開催されました。
第一部:講演会
特定非営利活動法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会 武田飛呂城氏より、開催地周辺のハザードマップを手に取りながら災害に備えるため、以下のように講演が催されました。
1)災害をイメージする
“自然災害”には地震だけでなく津波や風害、水害、雪害など様々な種類があります。自分の住んでいる地域にはどのような災害が想定されているのかを知ることが重要です。地震や水害など、それぞれの災害ごとにハザードマップ(防災マップ)が作成されている地域もあります。実際に災害が起きたときに、自分の住んでいる地域や、よく行く地域にどのようなリスクがあるのかを事前に知っておきましょう。
高齢者や障害を持った方など、通常の避難所では生活が困難な要支援者のために、避難所内に福祉避難スペースや、バリアフリー設備を備えた福祉避難所があります。通常の避難所生活が困難な場合には、こうした施設への移動も検討してください。希望者全員が移動できるわけではありませんが、避難所での生活が難しいことを、係の人に伝えてみてください。
先の熊本地震では指定難 病患者の多くが水やトイレ、睡眠といったことに困難したと回答しています。このような、多くの方が困ることに加え、患者個々に困りそうなことはしっかりと考え、普段から誰かと話し合うとともに準備をしておくことが大切です。
「指定難病患者が熊本地震後に困ったこと」に関する調査ー速報ー
2)被災後3日~1週間を生き抜く
被災後重要になるのは、自助、共助、公助です。自助は自分や家族での助け合い、共助は地域や知り合い同士による助けあい、公助は行政による支援です。被災直後は「自助7割、共助2割、公助1割」と言われています。被災時は自分だけでなく、消防や警察の人も被災者です。自分の身は自分で守ることが大切です。
災害時に1人で避難することが困難で、支援が必要な人の情報を事前に集約する“避難行動要支援者名簿登録制度”がある自治体もあります。地元の町内会などによる避難訓練などに積極的に参加し地域の人とつながりを持つことが大切です。普段から心がけておくと良いことに、次のようなものがあります。
●家の耐震化、安全な寝室づくり
寝室には背の高い家具を置かない、窓ガラスに“飛散防止フィルム”を貼る、照明器具はなるべく直付けタイプのものにする。
●食料と水の確保
最低3日分、できれば1週間分の水や食料を確保する。水は1人あたり1日3Lを目安に。回転備蓄法:普段から使う食材を多めに買っておき、最低○個以下になったら買い足すと決め、全て使い切る前に買い足していく方法。
●トイレの確保
災害時水が使えなくなったり、下水管が外れて水を流せなくなったり、トイレを使えなくなることがある。紙おむつや凝固剤、簡易トイレやペット用の猫砂などを用意しておく。
●薬の確保
災害時には必要な薬が手に入りにくくなることがある。主治医と相談し、可能であれば少しずつ多めに処方してもらう。可能であれば、外出時に数日分の薬を携帯するように心がける。災害時には医者にかかれなくてもおくすり手帳があれば、薬局で薬を処方してもらえる場合もある。
●電気で動く医療機器
外付けバッテリーがあれば最低2個以上の予備を持っておく。単三電池で動くタイプもある。手動式の呼吸器や吸引機もある。普段から、医療従事者の指導の下に練習しておくことが大事。
●災害発生時の医療
災害などで多くの傷病者が出た際、1人でも多くの方を助けるため“トリアージ”という方法で治療優先度を決定する。トリアージは1人あたり30秒程度で行われるため、自身の疾患の注意点を簡潔に伝える。カードにして財布などに入れておくのも良い。トリアージは1度で終わりではなく繰り返し行われるので、時間が経ってからおかしいと思うことがあったら伝える。
●リラックスする方法を持つ
不安や緊張、ストレスなどがあると体調にも悪影響を及ぼす。普段から自分がリラックスできる簡単な方法を持っておく。 (例:深呼吸、手や足や頭のマッサージなど)
第二部:意見交換会
第二部では10人程度のグループごとに分かれ、「普段実践している防災」「今後取り入れていきたいこと」といったテーマで意見交換を行いました。
参加者からは
・背の高い家具はなるべく置かず、倒れてくるリスクを低くしている
・1週間分の食料は常に家にあるように買い物に行く
・ポータブルトイレや紙オムツを用意している
・防災グッズの中にラップを用意しておく。ラップは皿の洗い物を減らすだけではなく長く引き出して紐状に縒る(よる)ことでロープの代わりに利用する。
といった、意見が出されました。
その他、医療器具のバッテリーに対する不安や避難経路の疑問など、いざという時の疑問やアイデアが活発に交わされました。
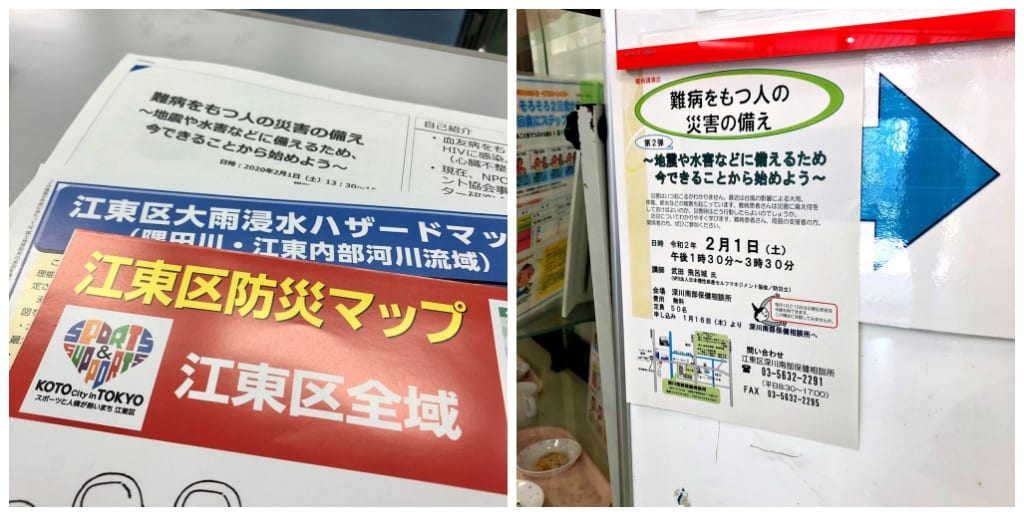
特定非営利活動法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会のHPは こちら