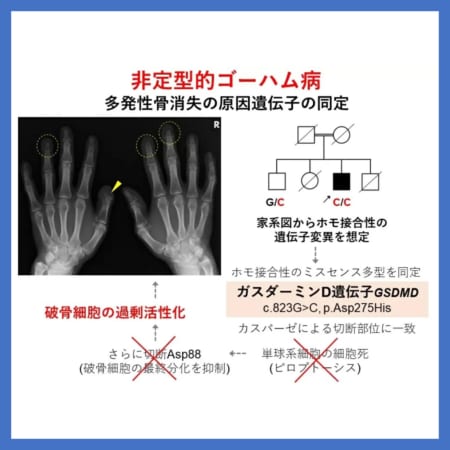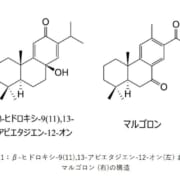新型コロナ後遺症と全身性エリテマトーデス(SLE)に類似性
関西医科大学の研究チームは3月31日、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の後遺症が、指定難病である全身性エリテマトーデス(SLE)と病態の一部で類似性を示す可能性があるという研究結果を発表しました。
全身性エリテマトーデス(指定難病49、SLE)は、免疫の異常により、全身のさまざまな箇所に炎症が起こる疾患です。発熱、全身倦怠感、疲労感、食欲不振、体重減少などの全身症状が現れます。
新型コロナに罹患した患者さんのうち、約2割の方が長期にわたる倦怠感や呼吸困難などの症状に苦しんでいるため、その原因や治療法の確立が急務となっています。
今回、研究チームは、新型コロナ後遺症外来を受診した患者さんの中から、世界保健機関(WHO)の診断ガイドラインに合致する39人の血液サンプルを収集し、解析を行いました。患者さんから同意を得た上で採取された血液サンプルは、匿名化され、関西医科大学のバイオバンクセンターに寄託されました。そして、この血清を用いて、免疫反応に関わるタンパク質である各種インターフェロンの量を測定し、その関連性を調べました。
Multiplex Elisa法で解析した結果、複数のインターフェロン間で正の相関関係が認められました。さらに、性別や年齢といった影響を考慮した解析においても、すべてのインターフェロン間に同様の相関が見られました。また、採取された血清に機能的なインターフェロンが含まれていることを確認するため、細胞に血清を暴露し、インターフェロンによって誘導される遺伝子のmRNA量を測定しました。その結果、Mx1遺伝子の発現量が、血清中のインターフェロンの量と正の相関を示すことが明らかになりました。
インターフェロンが病態形成の中心となる自己免疫疾患群は「インターフェロン病」と呼ばれ、その一つに全身性エリテマトーデス(SLE)が含まれます。研究チームは、公共データベースから新型コロナ後遺症患者さんと健常者の血液細胞における遺伝子発現情報を取得し、メタ解析を実施。その結果、新型コロナ後遺症患者さんでは、主に免疫関連の遺伝子、そして全身性エリテマトーデス(SLE)の病態に関わる一部の遺伝子に変動が見られました。
さらに、全身性エリテマトーデス(SLE)と新型コロナ後遺症の症状に一部共通点があることから、新型コロナ後遺症患者さんの血清中の抗核抗体群(抗DNA抗体および抗Sm抗体)の量を測定しました。その結果、すべての血清において、少なくともどちらかの抗体が検出されました。性別と年齢の影響を調整した解析では、抗DNA抗体と抗Sm抗体の量が、多くのインターフェロンの量と相関を示すことが示されました。
これらの結果から、新型コロナ後遺症の患者さんには、インターフェロン病、特に全身性エリテマトーデス(SLE)に類似した病態の要因が存在する可能性が示唆されました。さらに、統計的な手法である重回帰分析を用いて、抗DNA抗体と抗Sm抗体の量と症状との関連性を調べたところ、抗DNA抗体の量が多い患者さんでは、咳、鬱、脱毛、嗅覚消失、筋・関節痛といった症状が見られやすい傾向がありました。一方、抗Sm抗体の量が多い患者さんでは、発熱、不整脈、味覚消失といった症状との関連性が見られました。
以上の研究成果より、新型コロナ後遺症の診断において、抗DNA抗体や抗Sm抗体の測定が補助的な役割を果たす可能性が示唆されました。また、全身性エリテマトーデス(SLE)に対する既存の治療薬が、新型コロナ後遺症の治療に応用できる可能性も示唆されました。研究チームは、自然免疫を抑制する効果が報告されているヒドロキシクロロキンという薬剤に着目しているといいます。