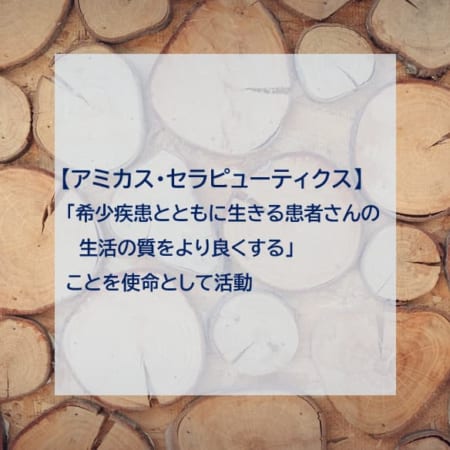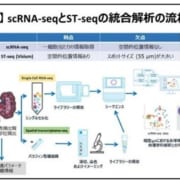らいそぞーむびょうライソゾーム病Lysosomal storage disease
指定難病19
小児慢性疾患分類
- 疾患群-
- -
- 大分類-
- -
- 細分類-
- -
ライソゾーム病
ゴーシェ病
ニーマンピック病A型
ニーマンピック病A型
ニーマンピック病C型
GM1ガングリオシドーシス
GM2ガングリノシドーシス
クラッベ病
異染性白質ジストロフィー
マルチプルサルファターゼ欠損症
ファーバー病
ムコ多糖症I型
ムコ多糖症II型
ムコ多糖症III型
ムコ多糖症IV型
ムコ多糖症VI型
ムコ多糖症VII型
ムコ多糖症IX型
ヒアルロニダーゼ欠損症
シアリドーシス
ガラクトシアリドーシス
ムコリピドーシスII型
ムコリピドーシスIII型
α-マンノシドーシス
β-マンノシドーシス
フコシドーシス
アスパルチルグルコサミン尿症
シンドラー病
神崎病
ポンぺ病
酸性リパーゼ欠損症
ダノン病
遊離シアル酸蓄積症
セロイドリポフスチノーシス
ファブリー病
シスチン症