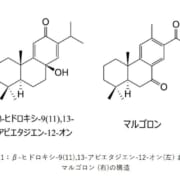自己免疫に関与するB細胞の働きに対する暴走制御因子を解明
九州大学生体防御医学研究所をはじめとする研究グループは2020年6月25日、免疫機能に関するB細胞が自身の組織を攻撃するスイッチの機能を果たしている因子を世界で初めて明らかにしたことを発表しました。B細胞は体内に侵入した病原菌などの異物を排除する働きがあり、免疫機能において重要な役割があります。B細胞が異常な活性化を起こすことで自身の組織も攻撃するようになり、自己免疫疾患が引き起こされます。疾患モデルマウスを用いた実験では、B細胞にあるTet分子を欠損させることで全身性エリテマトーデス(SLE)のような自己免疫疾患に似た症状が起こることも明らかになりました。
自己免疫疾患の発症メカニズム
B細胞はリンパ球の一種でありT細胞などと一緒に、体内に侵入した病原菌などの外敵に対する生体防御反応において非常に重要な役割を果たします。一部のリンパ球では外敵のみならず自分自身の組織を攻撃する働き(自己反応性)も持っていますが、普段は自己寛容と呼ばれるメカニズムが働くことで自己反応性は抑えられています。自己寛容に異常が起こることでリンパ球が自信の組織を攻撃しはじめ、自己免疫疾患が発症すると考えられています。これまでに自己寛容がどのように制御されているかは明らかになっておらず、自己免疫疾患の発症メカニズムについて不明でした。そこで研究グループはエピゲノム制御因Tet(Tet2,Tet3)に着目し、B細胞のみでTet分子を欠損するノックアウトマウスを作成しました。
Tet分子欠損による自己免疫疾患症状との関連性を解明
Tet分子をB細胞でのみ欠損するノックアウトマウスでは、リンパ組織における自己反応性B細胞のみならず、T細胞にも恒常的な活性化が起こっており、全身性エリテマトーデスのような自己免疫疾患に似た症状が起こることが明らかになりました。さらに、遺伝子解析の結果、Tet分子の欠損によってB細胞とT細胞の相互作用を促進するCD86の発現が上がっていることが示され、自己免疫疾患発症前にCD86の働きを中和するとリンパ球の活性化および自己免疫疾患症状が抑制されました。自己免疫疾患は特定の臓器や部位または全身に炎症症状がみられる難治性の疾患で、指定難病に指定されている疾患も複数あります。さらなる研究が重ねられることで、複数の自己免疫疾患に共通する発症メカニズムが解明され治療法の開発にも繋がると考えられます。
出典元
九州大学 研究成果