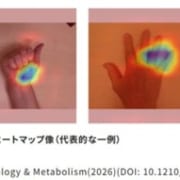抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎における間質性肺炎、新たな治療標的としてインターロイキン‐6に期待
東京医科歯科大学の研究グループは4月11日、大阪大学、筑波大学との共同研究により、抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎患者さんの間質性肺炎成立には、炎症性サイトカインのインターロイキン‐6が重要な働きをしており、特異的治療標的になりうることを突き止めたと発表しました。
膠原病のひとつである皮膚筋炎では、筋肉の炎症により筋力低下が生じたり、皮膚症状として特徴的な皮疹が現れたりします。その中でも、抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎患者さんでは、内出血を伴う特徴的な皮疹が現れ、間質性肺炎を合併する可能性もあります。この間質性肺炎を発症すると、急速に進行し死に繋がることもありますが、現在、病態生理解明は十分に行われておらず、高用量ステロイド投与などの非特異的免疫抑制療法をおこなっています。
現在、特異的自己抗体(筋炎特異的自己抗体)がいくつか同定されており、その筋炎特異的自己抗体ごとに臨床症状の特徴があることが判明してきており、患者さんの治療方針を決定する際に役立っています。
今回、研究グループは、抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎患者さんの間質性肺炎を模した新規モデルマウスを確立し、マウスMDA5全長タンパクを精製し、免疫賦活剤と共にマウスへ投与して免疫を惹起することで、マウスMDA5への自己免疫が誘導しました。
さらに、ウイルス感染症を模した免疫賦活剤を経鼻投与すると、1日で回復する肺傷害が起こりますが、MDA5に対する自己免疫が成立しているマウスでは、肺間質での炎症が延長し、線維化を伴って、間質性肺炎を呈してくることを見出しました。
間質性肺炎を発症したマウスの傍気管支領域には、特にCD4ヘルパーT細胞が浸潤しており、間質性肺炎を発症したマウスのCD4ヘルパーT細胞を健康なマウスに移入すると、肺炎が起こりますが、CD8キラーT細胞や免疫グロブリンIgGの移入では、肺炎を再現することはできず、今回の疾患モデルは、CD4ヘルパーT細胞が病原性細胞である、自己免疫疾患であることが証明されたとしています。
また、CD4除去抗体治療によってこの間質性肺炎発症を抑えられること、一方で、抗体を産生するB細胞系列を遺伝的に欠損しているマウスでは間質性肺炎を発症できる、つまり、B細胞はこの間質性肺炎発症に必須ではないことも見出しました。
さらに、間質性肺炎症惹起初期と完成時との肺組織を解析した結果、初期にはI型IFN反応性蛋白Mx1発現が上昇しており、I型IFN受容体を遺伝的に欠損しているマウスではこの肺炎を誘導できないものの、間質性肺炎の成立にはインターロイキン-6(IL-6)が主要な働きをしており、さらにはIL-6標的療法である抗IL-6受容体抗体療法によって間質性肺炎を治療できることを見出しました。
以上の研究成果より、抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎関連間質性肺炎では、発症初期にはウイルス感染症や免疫賦活剤経鼻投与によって引き起こされる、I型IFN発現などの自然免疫活性化が間質性肺炎の「土壌」として重要で、MDA5特異的CD4ヘルパーT細胞が間質性肺炎の「種」として病態を形成し、線維化を伴う間質性肺炎の成立には、IL-6が必要で、このIL-6が間質性肺炎の新たな治療標的として期待されるといいます。
なお、同研究の成果は、国際科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)」オンライン版に4月8日付で掲載されました。