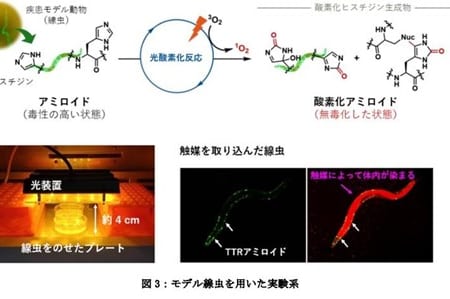潰瘍性大腸炎に関与する免疫細胞の役割を発見
順天堂大学をはじめとする研究グループは、潰瘍性大腸炎 (指定難病97) 患者の炎症部位において特定の免疫細胞が複数の細胞集団を形成していることを明らかにしました。さらにこの細胞集団中では、炎症反応に関わるインターロイキン26 (IL-26) を産生する免疫細胞が増加していることも明らかになりました。
背景-潰瘍性大腸炎に関わる免疫細胞と炎症反応因子
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に炎症が起き潰瘍ができる炎症性疾患で、国の指定難病にも指定されています。自己免疫性疾患のひとつであることが明らかになっており、下痢や腹痛、血便などの症状がみられ、緩解と再燃を繰り返します。近年の薬剤開発の結果、生物学的製剤や免疫抑制剤などの新規薬剤の登場のおかげで、徐々に症状を抑えやすくなってきました。しかしこうした薬剤は、小児や高齢の患者には使用しづらく、また、医療費の高額化や薬の副作用など課題は多く残っています。病態にはまだわかっていないことも多く、根本的な治療法の開発に向けた研究が求められています。潰瘍性大腸炎患者は大腸の粘膜層に、免疫細胞の一種であるCD4 T細胞とCD8 T細胞が関与していることは知られていましたが、どの細胞がどのように炎症反応に関わっているか不明でした。
結果と展望-CD8 T細胞による発症メカニズムを解明
今回の研究には、オックスフォード大学病院で内視鏡検査を受けた潰瘍性大腸炎患者または健常者の大腸組織が用いられました。大腸組織中に含まれるCD8 T細胞の遺伝子発現パターンを解析したところ、14種に分けられる細胞集団を形成していました。さらに、潰瘍性大腸炎患者と健常者を比較したところ、潰瘍性大腸炎患者ではインターロイキン (IL-26) を産生するCD8 T細胞と、細胞傷害作用を持つCD8 T細胞の割合が大きく増加していました。IL-26は免疫細胞が作る炎症関連物質の一種です。今後さらにCD8 T細胞の役割やIL-26との関連性が明らかになっていくことで、潰瘍性大腸炎のみならずクローン病などの難治性腸疾患の病態解明にも繋がると期待されます。
出典元
順天堂NEWS