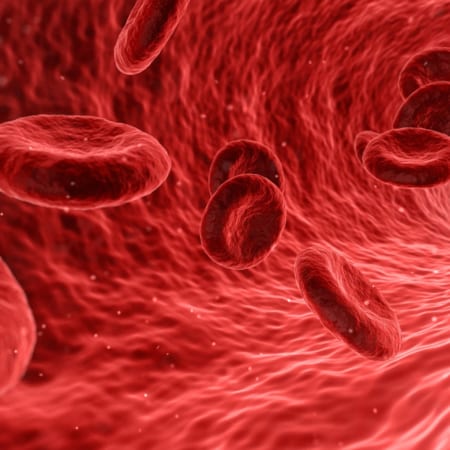病原性B細胞の発生・維持の仕組みをモデルマウスで解明、全身性エリテマトーデス(SLE)等の新たな治療法開発に期待
九州大学は4月19日、老齢マウスおよび自己免疫疾患モデルマウスを用いた研究により、特殊なB細胞である病原性B細胞(ABCs)が自己抗原から持続的な刺激を受け、その結果として、B細胞受容体(BCR)が細胞内に取り込まれ、常に活性化していることを明らかにしたと発表しました。
今回の研究では、老化や自己免疫疾患において病態を悪化させることが知られている、ABCs(Age-associated B cells)がどのように発生し、維持されるのかという未解明の課題を検討。研究グループは、老齢マウスおよび自己免疫疾患モデルマウスを用いた実験を行いました。
その結果、ABCsは自己抗原からの持続的な刺激を受け、その結果としてB細胞受容体(BCR)が細胞内に取り込まれ、常に活性化している状態にあることを突き止めました。また、アナジーB細胞に特徴的に見られる遺伝子「Nr4a1」が、ABCsへの分化を抑制する役割を持つことも判明。さらに、ABCsにおいて恒常的に活性化しているBCRのシグナル伝達経路における重要な分子として、「ブルトン型チロシンキナーゼ(Btk)」を特定しました。このBtkの阻害薬を老齢マウスや自己免疫疾患モデルマウスに投与したところ、ABCsが選択的に減少し、自己免疫疾患の症状が改善されることも確認されました。
今回の研究成果は、老化と自己免疫の間に存在する深い関連性を示すものです。この発見により、病気の原因となるB細胞をピンポイントで除去することで、全身性エリテマトーデス(指定難病49、SLE)のような自己免疫疾患の病態を根本から改善し、副作用を最小限に抑えた治療法の開発につながることが期待されるといいます。
なお、同研究の成果は、「Science Advances」に4月19日付で掲載されました。