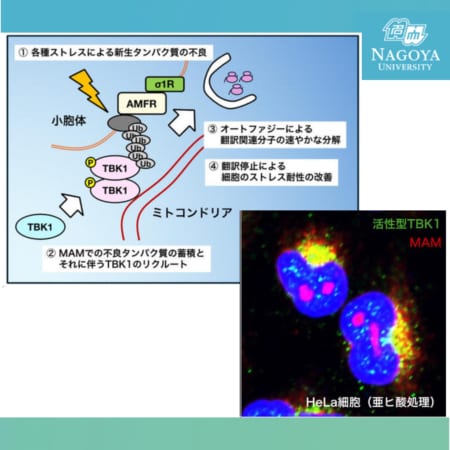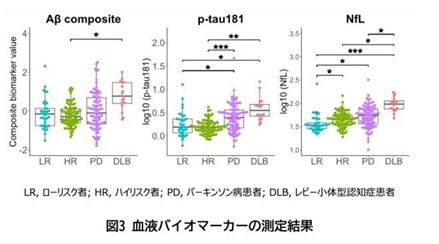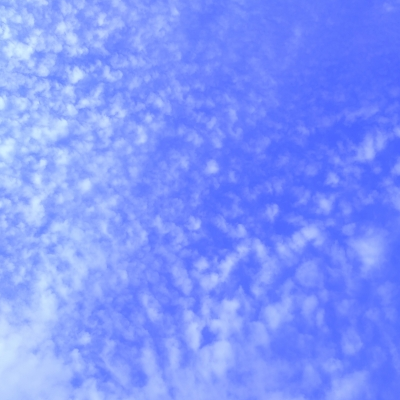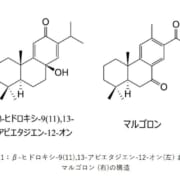歯周病菌と低酸素が多発性硬化症の進行に関与
東京科学大学は7月8日、東京大学、昭和医科大学、大阪大学、関西医科大学との共同研究により、歯周病原細菌が免疫細胞であるマクロファージに対して、低酸素誘導因子HIF-1αに依存して、自然免疫反応のひとつであるインフラマソームの活性化を誘導し、それによって多発性硬化症の増悪を引き起こすことを明らかにしたと発表しました。
歯周病は、口の中だけでなく、糖尿病やアルツハイマー病、関節リウマチなど全身の様々な疾患の発症や悪化に関連していることが近年の研究で示されています。歯周病患者さんの口の中から高頻度で検出されるPorphyromonas gingivalisという細菌は、酸素が少ない環境でしか生きられない性質を持っていますが、これまでの研究では、この細菌が本来生息する低酸素環境下での免疫細胞の反応については、ほとんど調べられていませんでした。
今回の研究では、Porphyromonas gingivalisが低酸素環境下にある時、免疫細胞の一種であるマクロファージに対して、「HIF-1α」という低酸素誘導因子に依存して、インフラマソームの活性化を誘導、炎症反応を強めることを発見しました。このインフラマソームの活性化亢進が、自己免疫性神経脱髄疾患である多発性硬化症の症状を悪化させることにつながる可能性が、マウスを用いた実験で示されました。
以上の研究成果は、酸素濃度が歯周病原細菌による全身の炎症にどのように影響するかという、これまでにない新たな炎症誘導のメカニズムを提示するものです。これらの結果は、歯周病と神経疾患の関連性について新しい視点をもたらし、多発性硬化症をはじめとする全身性疾患の病態理解や、今後の治療法開発への貢献が期待されています。
なお、同研究の成果は、「Cell Death Discovery」オンライン版に6月10日付で公開されました。